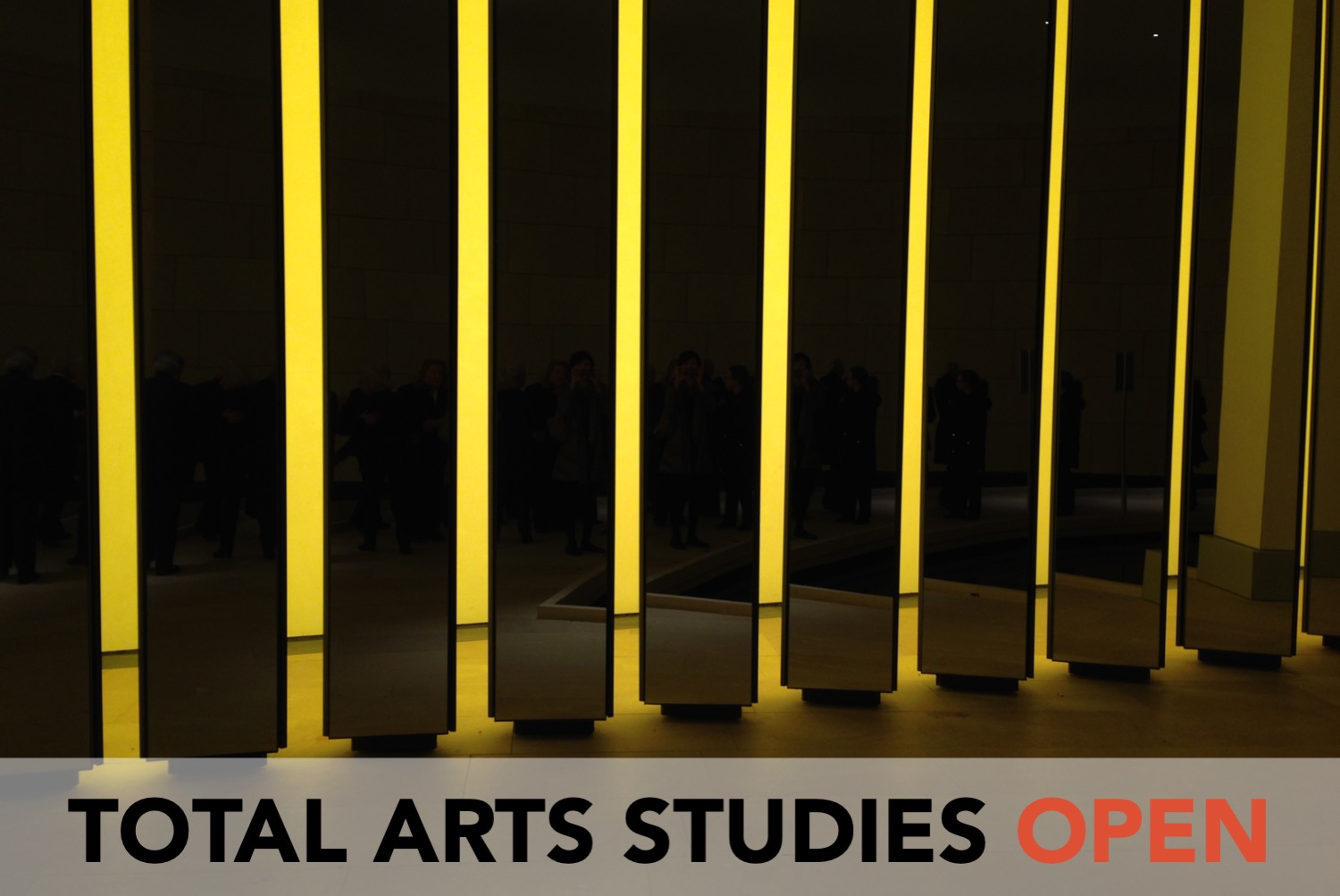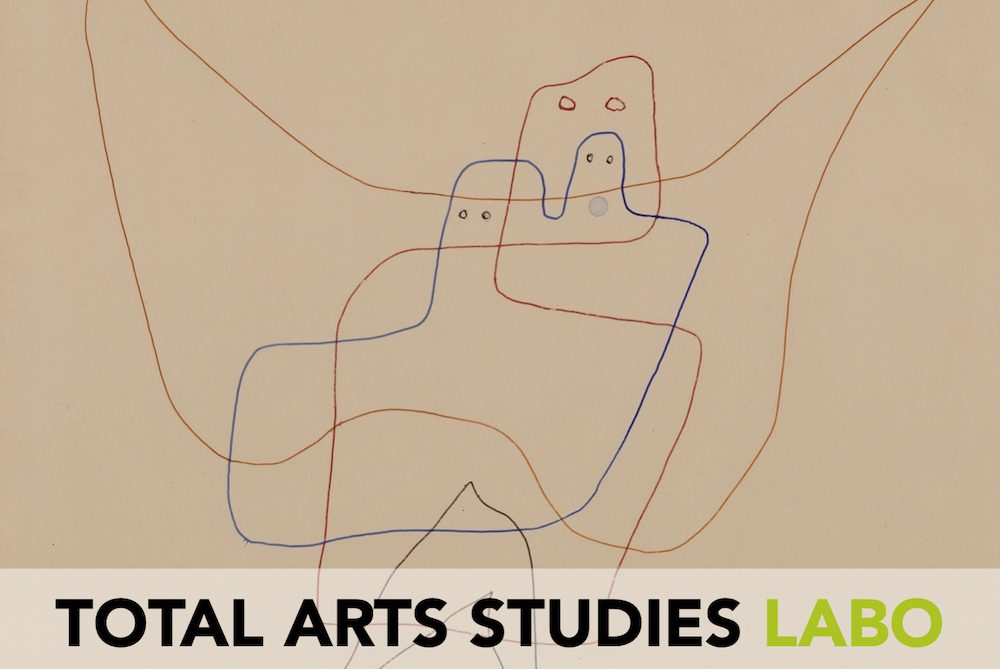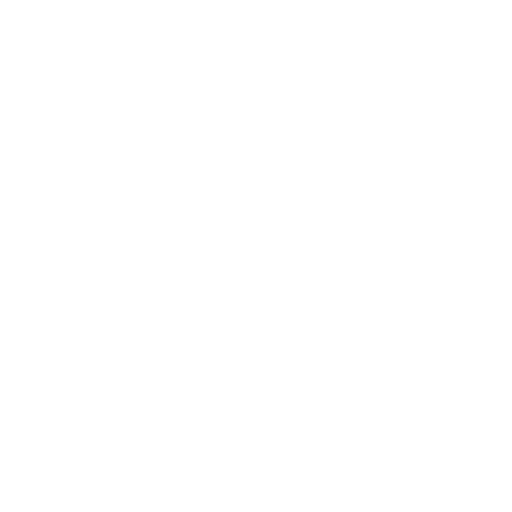
Taro Nettleton
テンプル大学ジャパンキャンパス上級准教授。専門分野は現代美術、視覚文化研究。
ネトルトン・タロウ(テンプル大学ジャパンキャンパス上級准教授)氏によるレビューです。
ネトルトン・タロウ(テンプル大学ジャパンキャンパス上級准教授)
去ること2/13(土)に私はテート・モダン インターナショナル・アート部門 シニア・キュレーター(写真担当)中森 康文氏を招いて開催されたAIT主催のウェビナー「アクティヴィズムとしての写真表現 − ザネレ・ムホリを紐解く」を聴講した。(閉鎖中のテート・モダンでは、現在開催のムホリの個展も閉鎖中であるが5月17日に同館再オープンと共に一般公開とのこと。)ムホリは、英語圏では近年様々なメディアで紹介されている著名なヴィジュアル・アクティヴィストである。自身を含む南アフリカの黒人LGBTQIA+コミュニティーの存在を主張し、黒人LGBTQIA+の人たちの表象を増やし・多様化するためにドキュメンタリーやポートレート写真を作っている。クィアな黒人の生活を可視化するため、写真の基本的な「記録装置」としての役割を持った作品群であり、ムホリ自身、「[私にとって]最も重要なのはコンテンツです。誰が写っていて、なぜその人物がそこにいるか」であると説明している。
ムホリは自分のことを「アーティスト」ではなく、「アクティヴィスト」とするが、それはアートが一手段にすぎないという意味だろう。そう捉えた場合、この作品群を観るにあたって重視されるべきなのは、aesthetics(美学)ではなく、ethics(倫理)だと思うので、ここでは作品の様式的な評価は割愛させてもらうが、前提として、様式的評価なしにテート・モダンのような権威をもつ美術館に入ることは許されないとだけ書いておきたい。そして運動性を重視した作品も、とかく美術館という制度の中では審美化されてしまうことを、今回のウェビナーで改めて認識した。無論このような美術史的なフレーミングがあってこそ、ムホリのアクティヴィズムが美術館へ参入できるのであり、アクティヴィストの作品が展示されることはとても良いことだ。おそらく美術館の制度的背景もあり、シニア・キューレーターの中森氏は、南アフリカに於ける黒人LGBTQIA+コミュニティーの事情やムホリの背景をとても分かりやすく説明しながら、写真の参加者のポージングに見て取れる「コントラポスト」やセルフ・ポートレートのシリーズの中で使われている小道具のシンボリズムを紐解くという、美術史的な説明をすすめ、また、本展覧会がもたらす効果としては、これまでの美術史と美術館の在り方自体の多様化が挙げられる、と言及した。
作家の意図をパフォーマティヴに伝えるためには、もう少し画期的な紹介方法が必要だったかもしれない。ウェビナーの形態も、パネリストのみをスクリーンに映し、参加者を受動的な、表象されない観者とし、ムホリが求めるアクティヴィズムとは遠く離れていた。ムホリは未来に向け、[作品と運動を通して]「どんな空間でも形成できる」と語っているが、今回のウェビナーは古典的な空間へのとどまりを感じた。アクティヴィティーを継続するためには、鑑賞ではなく、観者を突き動かす紹介の仕方が適当であったはずだ。
なぜ南アフリカの黒人LGBTQIA+の人たちのポジティヴな表象を増やす必要があるのか?それはイメージの問題だけではなく、中森氏の説明にもあった通り、 南アフリカでは黒人のレズビアンやトランスジェンダーの人たちが日常的に迫害・抹殺されているからである。この写真はつまり、存在を否定されてきた人たちを記録し、その記録を通して、その人たちを、今までその人たちを削除・拒否してきた公共空間に運び込む実践である。これらの「公共空間」は、人種隔離政策があった南アフリカでは排他的であった。 作品展示を通して、ムホリは歴史的に黒人クィア・フォビック(黒人クィアの人々に対して嫌悪/恐怖心を示す)だった空間を変換させようとしているのだが、歴史的にクィア・フォビックや人種差別的だった空間はもちろん南アフリカだけではなく、英国にも日本にも存在する。この作品は、黒人LGBTQIA+の観者たちに、黒人LGBTQIA+の参加者(ムホリは「被写体」とは呼ばない)のポジティヴな表象を体験する機会を与えることによって、自分もコミュニティーの一員である認識と、コミュニティー創作の可能性を示唆する装置でもある。よって、ムホリの作品は黒人LGBTQIA+のコミュニティーを「反映」するだけでなく、「生産」することに重点を置いている。
ムホリの実践において、当事者と行為主体性は極めて重要な概念である。その意図を汲み取るのであれば、黒人、レズビアン、トランスジェンダーなパネリストがいても良かったと思うし(実際にはシスジェンダーのアジア人男性とアジア人と白人のミックスの男性、シスジェンダーのアジア人女性二人)、この文章を書くのも自分より適した人がいるはずだと思ってしまう(著者はシスジェンダー、アジア人と白人のミックス男性)。ジョン・バージャーが『イメージ-視覚とメディア』で指摘しているように、作品を美術史的な様式重視の文脈に落とし込むことによって、本来参加者であるはずの観者から遠のかせてしまうことがある。特に運動として捉えられるべきムホリの作品について考えるとき、私たちは作品中の政治的背景を理解しながら、更にそれらが示唆する一連の問題が、私たちにも身近であることを検討するべきだろう。ムホリの作品が題材としている問題は南アフリカの課題でもあるが、グローバルな課題でもある。例えばロンドンでは、2020年10月までの一年間に3,111件の性的指向に基づいたヘイトクライム(*1)があった。アメリカでも黒人のトランスジェンダーの人たちが日常的に殺されている。
では日本ではどうなのか?ヘイトクライムはあるのか?日本の主流のメディアや美術館にレズビアンや黒人やトランスジェンダーの人々の多様な表象はあるのか?運動としての作品は観者の活性化を狙うはずであり、参加者から求めるべき反応は「これから自分に何ができるだろう?」という未来に向けた探求心だと思う。「日常性への接近」は前衛美術のテーマとして捉われがちだが、アクティヴィスト・アートにも不可欠だ。アート作品と観者の日常生活の関連性を問うて、初めてクィア・フォビックな空間を変えることができるのではないだろうか。
*1 参照元:https://www.bbc.com/news/uk-england-london-51049336
TOTAL ARTS STUDIES とは?
TOTAL ARTS STUDIES
芸術を、これからの時代を生きぬくための「道具」として捉え、社会を多角的に考察しながら、誰もがアクセスできる学びの場を目指します