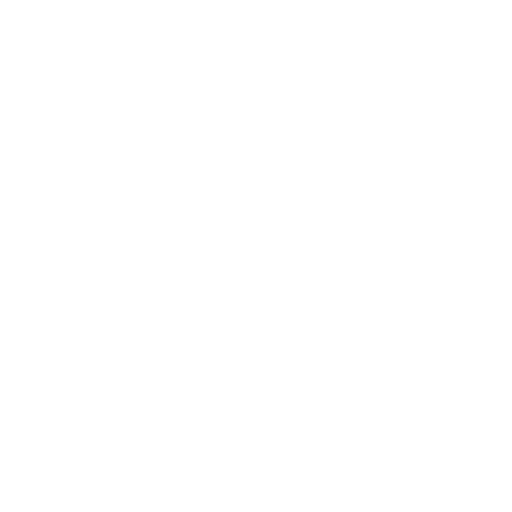
東海林慎太郎(AIT)
プロジェクト・マネージャー
2020年より、世界が新型コロナウイルス感染症によるパンデミックを経験するなか、アーティストが国内外を移動することを前提としていたアーティスト・イン・レジデンスプログラム(以下、 AIR)は、その内容だけでなく意義にも問いと課題が与えられました。
あらゆるプログラムがオンライン化に傾倒する今、アーティストにとっての「移動」と持続的なAIRに対する考えを刷新できるのか。2003年からAIRを始めて以降、さまざまな表現者を招き、また海外に派遣してきたAITも、環境に配慮した移動を例に、これまでの当たり前とされた「移動」の概念を問い直した先にある新たな方法論に関心を寄せています。
そこで、改めてAIRの活動と立ち位置を見つめる第一歩として、2021年3月に行われた本ラウンドテーブルでは「art for all」より二人のアーティスト、村上華子さんと白川昌生さんに加えて、国内でAIRを実践する小田井真美さん(さっぽろ天神山アート スタジオ)、日沼禎子さん(KESEN AIR)、勝冶真美さん(京都芸術センター)をスピーカーに、オブザーバーとして菅野幸子さん(AIRリサーチャー)、石井潤一郎さん(ICA京都)を迎えました。
2021年3月22日(月)オンライン
レポート:王聖美
アーティストとAIRとっての移動、AIRに期待されることとは?
10年前に日本を離れ、フランスを拠点に活動している村上華子さんは、自身が移動を重ねてきた経験から、アーティストの活動にとって最適な拠点がどこなのかは移動してみないとわからない、移動先で出会った人やそこでの経験が、作品の展開や自己理解に繋がると感じています。そして、その可能性が制限されている現状を踏まえ、アーティストの移動についてあらためて考える機会として、3月10日に開かれたart for all「アーティストのための実践講座 アーティストの生活と移動」を企画しました。イベントでは、さまざまな移動の例が紹介され、拠点を直島に移した下道基行さん(アーティスト)の活動と子育てを含む生活の話や、犬も「家族」として滞在できるAIRを探したうしおさん(アーティスト)の話は、制作やキャリアのためだけではなく、様々な変化に影響されつつも生活と並列してあるアーティストの移動を表すものでした。

自宅暗室内での作品制作の様子をオンラインで中継した。 From Here to There, 2020, courtesy of Japan Society, New York
ジャパン・ソサエティ「From Here to There」
From Here to There – Hanako Murakami: Making Imaginary Landscapes 自宅暗室内での作品制作の様子をオンラインで中継した動画
Virtual Opening: Artists’ Presentations + Discussion
さっぽろ天神山アートスタジオでAIRディレクターを務める小田井真美さんは「アーティストから日常を切り離し、制作に集中するための時間と場所を提供する」かつてのAIRの姿勢は、変化するアーティストのニーズに既に合わなくなっていると話します。元ホテルの施設環境を生かした天神山アートスタジオでは、アーティストやリサーチャーが自己負担をしながらも、家族同伴の滞在を選べたり、期間と活動内容が柔軟に設定できる自由度の高いAIRを実践していることを紹介し「アーティストの求める環境に応えることが課題であり、期待されている」という実感から、今後のAIRの柔軟性やプログラムの多様性を問いかけます。
東日本大震災後に地元企業とKESEN AIR(「陸前高田AIR」から2020年より改称)を立ち上げた日沼禎子さんは、被災した地域の人たちとアーティストのお互いの生活を通してアートのあり方を考え、震災後のまちづくりとつながる国内外のアーティストをサポートしています。KESEN AIRに家族と一緒に滞在し、長期的または継続的にライフワークとして関わっているアーティストが多くいることは、アートと生活を切り離すのではなく「生活を一緒にできる場所」という一つのAIRの姿を実現しています。
地域から世界に繋がる可能性を探る
白川昌生さんは、1970年代に渡欧してフランスとドイツで哲学と美術を学び、1983年に帰国。以降、群馬を拠点に活動しています。若い世代のアーティストに制作や発表を条件とせず、リサーチに集中するAIRがあってもいいと提言し、作品に用いたモチーフが、思いもよらない巡り合わせを引き寄せた自身の経験を紹介しました。
群馬の山奥には廃材が捨てられる場所が多くあり、白川さんはそうしたものも素材にしながら作品を制作していましたが、ある時、過疎の村でドイツの炭鉱で働いていたという人に出会います。探ってみると、その地域にはかつて鉄鉱石の鉱山があり、資源が底をついたため、坑夫たちは北海道の旭川にある炭鉱へ集団で出稼ぎに出向き、今度は旭川からドイツのツォルフェライン炭鉱(1990年代に大規模の再開発が行われ、近代化遺産の再開発成功例として世界的に知られる所になった)に派遣され、群馬に戻っていた、という移動の歴史が浮き彫りになりました。他にも草津温泉や伊香保温泉は、ハンセン病の治療や救済に関わったドイツ人医師たちやキリスト教宣教師たちと深く関わりがあるなど、地域の歴史を辿ると、国を超えた別の場所や文化圏に接続する醍醐味を紹介しました。
場所の歴史的な文脈を最大限に広げれば、ローカルな場から世界に接続するという発想には、必ずしも移動を伴わないAIRの序章のような可能性があるのではないか、と堀内奈穂子さん(AIT)はコメントします。オンラインを用いたAITのAIRでも「移動ができないこと」から生まれる新たな発想、例えば毎日飲むコーヒーからブラジル、エクアドルやインドネシアを連想したり、日常で口にするものや手にするものから離れた地域を想像することも可能なのかもしれない、と東海林慎太郎さん(AIT)も付け加えます。
危機がもたらした協働
私たちが経験した共通の困難を機に、オンラインを一つの場として「art for all」のように提言をも見据えた共同体や大小さまざまな協働が芽生えています。
コロナ禍で美術界が受けたインパクトに対し、日本では給付金や助成金対策が遅れ、特に現代美術分野に対しては更に後手になりました。そこで、主に現代美術に携わる関係者の組合のようなものを作れないか、という動機から「art for all」が発足しました。約5000人の署名を集めた<美術への緊急対策要請書>を政府に提出するとともに、アーティストの生活と労働環境の改善や自らを取り巻く問題をよく認識する必要があると考え、先の「アーティストのための実践講座」を始めました。今後は「アーティストの労働問題」もテーマに、映画や演劇界のユニオンのあり方、美術界の労働闘争の歴史、海外のユニオンの活動事例を学び、時代と実状に合う共同体の形を探ります。
AIRをインストールし直す
勝冶真美さんは、市民へ還元するAIRの公共的役割として、アーティストの目的や行うことを市民にもプラスになるようなものにコーディネートすることが大切だと言います。京都芸術センターでは、今年度に招聘する予定だったのが来年度に延期となった2組のアーティストのプレリサーチとして、市民とのオンライン交流が行われましたが、参加者の顔が画面に見えるZoomでイベントを実施することは、リサーチの対象に今まで以上に意識的になり「コミュニティ」という抽象的になりがちな言葉と視点を、絞り込んで考える良い経験だったと話しました。一方、こうした活動がオンライン上にあるままでは、不特定多数の市民に届くのは難しいと感じ、館内の大型モニターで活動を上映したり、更には(大型モニターを持って)AIR団体が街に出て行くなど行動的な意識が必要だという発想も共有しました。


日沼さんは、文化事業の公共性についても問い直してきました。アーティストが長期的に地域と関わることが特徴のKESEN AIRでは、オンラインでありながら参加者とアーティストのコミュニケーションが実感できる身体的なワークショップが行えたことを振り返り、地域に対しては、新聞が家に届くようなイメージでタブロイドを発行することを考えています。


小田井さんは、もとは作品発表を重要視しない性格を持つ天神山アートスタジオのAIRで、コロナ禍においては、展覧会を行うことが市民への接続に手応えがあったことを振り返り、美術と関連しないと思われるまちなかにも作品をインストールすることで、繋がりを積極的に生み出した成果について触れました。

撮影:小牧寿里 ©︎ヒジュン・チェ / Heejung Choi 提供:さっぽろ天神山アートスタジオ
AIRのDNAを書き換える
こうして村上さんと白川さんと対話がはじまったのをきっかけに、もっとアーティストとAIR団体の対話を継続させ、AIRのDNAを書き換えていきたい、と東海林さんはAIRの未来に期待を寄せつつも、今できることを問います。
小田井さんは、AIRを行うための資金のひとつである補助金の性質が更新され、成果発表などの事業型からアーティストの活動そのものに拡張することの必要性について触れます。日沼さんは、芸術を媒介とした感動、つまり「良い記憶」が、芸術祭やAIRにもう一度赴きたいというモチベーションになり、その「良い記憶」は「マイストーリー(自分の物語)」が作られることで生まれることを説明します。そして、アーティストと地域の人にとっての「マイストーリー」を作ることを公共の場で実現してゆきたいと話しました。勝冶さんは、オンラインがオンサイトの代替ではなく、意思をもった選択肢としてのオンラインレジデンスとして存在すると考え、AIRの幅が広がることは運営者にもアーティストにもいい機会になると展望しました。
最後に、オブサーバーのお二人も、それぞれの見地と経験からコメントを共有しました。
立ち上がったばかりのICA京都でAIRを専門にアーティストを海外に送り出すサポートを行う石井さんは、村上さんのアーティストの移動の話に応答し、最適な場所を目指していくと、究極はそこに「レジデンス(滞在場所やプログラム)があるか」ではなく、移動先でアーティストが行う活動をサポートできるシステムがレジデンスの枢軸ではないかと言います。一方、日本のAIRシーンを長年見つめ、文化政策を研究する菅野さんは、インフラ整備、AIRの多様性、デジタルの活用の3点を指摘しました。その中で、アーティストとAIR団体が対話するこうした場が増えることを奨励しました。
AITでは、今後もAIRの発展と継続を試みながら、アーティストや関係者との対話を重ね、生活 の変化や複雑な時代に呼応しながらプログラムづくりを行っていきます。そうしたアイディアの構築に向けてAIRへの視点を相対化、複数化する対話を継続させます。
RESIDENCY とは?
RESIDENCY
海外の文化機関や財団との協働を通じて、多領域で活動する芸術家や研究者を日本に迎え、知識と経験を共有する国際交流の場を創出しています


