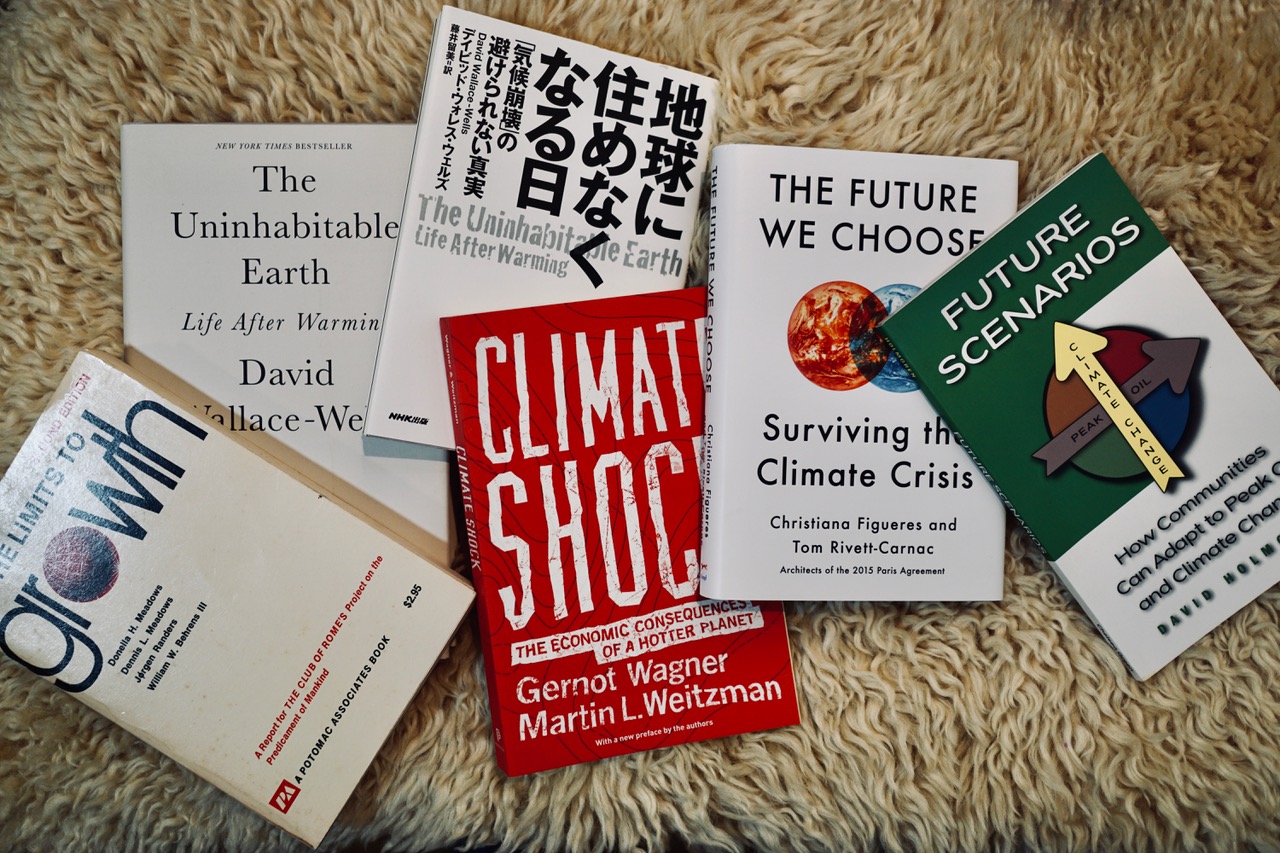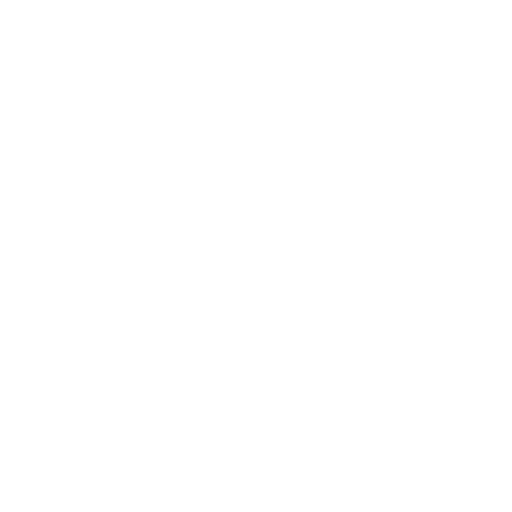
ACCJ Team
野村政之さん(信州アーツカウンシル ゼネラルコーディネーター )インタビュー
「気候危機という現実に、アートはどう応答できるのか?」。その問いの最前線にいる人々に、ACCJが活動内容や思いを聞くインタビューシリーズを開始します。初回は、長野県で先駆的な試みをおこなう信州アーツカウンシルの野村政之さん。枠を越え、多様な人々とつながりながら試行錯誤を重ねてきたその足跡には、表現と社会の関係を見つめ直すヒントがあります。全3回にわたる本インタビューでは、プロジェクトの背景からアーティストの変化、今後の展望までを伺いました。聞き手は、地元・長野県で野村さんと親交の深いアーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]のロジャー・マクドナルドです。
第2回「感性とサステナビリティが一緒になった“気持ちよくて安心”を目指したい」
「自分にもなにかできる」という意識を持っておく
——いまの資本主義社会では、100%サステナブルな生き方は不可能に近いですよね。いくら自給自足していると言っても、産業システムに頼らざるを得なくなることが必ずある。この矛盾のなかで気候危機に取り組もうとすると「偽善だ」と言われてしまうこともある。それを恐れて動けなくなってしまうアーティストも少なくないなかで、野村さんはなぜ乗り越えられているんだろう?
まず自分の生き方として、どうでもいい価値観に縛られて生きていきたくないというのがあって。たとえば売上至上主義で売上を上げないとクビになる会社にいたとして、自分はそのゲームはたぶん楽しくないと思うんです。
アートは、分からない状態が許容される社会だと思うんですよ。答えのない問題がいっぱいあるなら、それぞれの形で答えを出そうと頑張ったほうがいい。「解決できなくても、自分にもなにかできる」という意識は、みんなが持っていたほうがいい。たとえば、都会に住んでいるからという理由で「なにもできない」と自分を押し込めてしまうのはやめたほうがいい。都会に住んでいる人でもなにか手立てがあるんじゃないかと思うし、「ない」って思わされていることがすごい問題があるっていうか、別に地方に移住するっていうことも誰も止めているわけでもない。ただ都会では自分にはなにもできないと思わせる力が働いちゃっていて、それが本当に我々も含めたみんなの問題としてあると思うんですけど。
——私も移住して15年経ちますけど、なんとなく、そういう感覚は都会にいたときと変わったなってよく思いますね。
都会から移住してきた人がよく言うのは、「都会にいたときは自分にはなにもできないと思っていたけど、地方に移住して小さな社会に入ったら、自分とは違う能力や専門性を持った人たちと協力できる関係性が作れたりして、自分にもできることがあると感じられるようになった」ということ。たとえば、荒れた森を自分たちで再生させた里山のアート拠点「奏の森」の人たちは、木を切って平らにして水道管を引いたり電気工事したりと、自分たちの友達関係のなかからできる人を調達して、すべて自力で小屋を建てちゃっている。それによって大きな借金をすることもないし、ゴミを大量に出すわけでもない。


そういうやり方を見ていると、やっぱり大事なのは人の発想と姿勢なんですよね。奏の森のみなさんは、自分たちだけじゃなくていろんな人の技術を借りてやっている。これを自分に当てはめた場合、まだできることがいろいろあるかなと思ったりします。
現代は、家を建てるのは専門の業者さんにやってもらって、自分の家なのに建築中は家のなかに入れないみたいな状況だったりしますが、それってたかだか近代に入ってからの産業システムとしてのあり方なんですよね。本来は自分たちでできることを産業システムのなかに嵌めて、「こっちのほうがいい」っていう価値観を作ってしまった。その価値観をずらせれば、自分で自分のいる場所を作るほうが面白いし、環境負荷も低いよねってなるかもしれない。
——奏の森ほどはできないとしても、これくらいなら自分にもできるかも、みたいに考えてもらえるといいよね。
そう。もちろん、手に入らないものは“買う”必要があるわけで、そこまでぜんぶを否定するのではなく、おたがいが自立した形で“交換”できるような軸足を作りたいんです。僕も含めて、軸足なしにぜんぶ資本主義に捨て身でダイブしちゃっている人が多いと思うんですよ。そうじゃなくて、「これぐらいの食べ物は自分で採れているから、市場を経由せずに生きられているな」っていう安心感があれば、もっと自由にいろんなことできるんじゃないかと。
僕も今はいろんなところから給料をもらっていて、それで自分を生かすこともチャレンジすることも両方やらなきゃいけない。でも本当は、自分を生かすことのいくばくかを給料のような市場を通過したもの以外で調達したい。みんながもっとそれをやれば、“環境負荷も少なくて楽しくて気持ちいい”に近づける気がするんですよね。
――すごく大事な話ですね。ACCJをやっていても思うけど、こういう活動は「スイッチを押してすぐに結果が出る」ようなものではまったくなくて、じわじわ変わっていくという感じがあります。だからすごく忍耐力が必要だし、資本主義のスケール感とか時間軸とは違う感覚にアップデートしなくちゃいけない。そういう長期的な時間軸のなかで、結果はすぐには出ないかもしれないけれど、実験しながら付き合っていけたらいいよね。
安心と気持ちよさの両方を目指したい
——私は、アートがもともと想像を一つの大事な資源としてきたセクターだからこそ、この問題に真剣に取り組まなくちゃいけないと思っていて。絵を見るときに自分の想像を拡張するように、気候問題を考えるときにも、身の回りの半径5メートルや10メートルだけではない、いわば惑星的なパースペクティブを持つ必要があると思いますが、野村さんにはそれができている。どうしたら、日本のアーティストやアート業界がもっとそういう視点を持って、気候アクションに対してリーダーシップを発揮できるようになると思いますか?
気候危機を受け入れづらいアーティストがいるとしたら、いちど自分に問うてみてもらいたいんですよね。「狭いゲームのなかでプレイしているだけなんじゃないか」と。あなたのやろうとしているアートはどんな価値に向かっていて、どんな価値を否定しようとしているのか。自分たちの作っている文明社会が地球環境を損ねる事態にいまなっているわけだけど、そこにおいてアーティストだけが特別じゃないから。
資本主義の仕組みにかなっていたほうが儲かるしラクだってことは、多くの人が分かっていると思う。だから、放っておくとそっちに流れていってしまう。でも、面白がったり、気持ちいいなとか綺麗だなとか、そういう感性的な価値とサステナビリティが一緒になれば、「安心」と「気持ちよさ」があると思うんです。アートに関わる人間として、僕はそれを目指したい。要は、プライベートジェットで来る人のために作品をつくることを僕は楽しめない、という感じなんです。やっぱり、森のなかで気持ちのいい体験をしながら「いいな」と思えるものを追求していきたい。
そういう点で、アートはいろんなチャレンジができる場所だと思うんです。みんな、それぞれのクリエイティビティとかイマジネーションを使ってチャレンジしようぜ、と。そのための場所としてアートという場所があるし、アートには今ある社会の形や生き方に対するシミュレーションや社会実験の側面もあると思うんです。そういうアートの性質を上手に使っていけば、ほかの領域よりも先んじて歩みを進めることができるんじゃないかなって考えています。

——信州アーツ・クライメート・キャンプは3年目に入ると思いますが、今後のプランはなにかありますか? 信州アーツカウンシルは助成機関だから、たとえばグリーンポリシーやサステナビリティガイドラインなどを作成して助成対象に環境問題への取り組みを促す、とかいろんなやり方があると思うけど。
自分たちがやるときに大事にしたいのは、よっぽどひどい環境破壊はダメだと思うけど、普通に活動することにロックはかけたくないっていうのがあるんですよね。だからもしガイドラインをつくるとしたら、そのやり方は非常に工夫する必要がある。あまり上から権力的にやらないほうがいいのかなと。要は「楽しくて気持ちいい」みたいな方向に持っていきたいんですよ、どうしても。
誰がアクションしてもいいし、ガイドラインとかルールで縛らなくてもいい。「こういうやり方もあるね、こうやっても面白そうだよね」っていう雰囲気の場を作って、いろんな人がいろんなところから自分の意思でアクションしてくれるような長野県にしたいですね。

(第3回につづく)
編集・構成:木下悠
「信州アーツ・クライメート・キャンプ」の取り組みと意義について。地域の多様な人々と協働しながらアートを通じて気候危機に向き合い、文化・環境・暮らしの新たなつながりを探る実践とは。
第3回「2019年10月、あの災害からみんなの意識が変わった」
信州アーツカウンシルが気候危機に先進的に取り組める理由と課題。「信州の多様な文化芸術を、多様な主体が支える」ための環境づくりについて。
気候危機とアート とは?
気候危機とアート
アートがもつ表象の力、美術史や言説と気候危機の関係、そして具体的な実践について、AITの活動全体を通じて追求していきます。アート・オンライン講座「崩壊の時代の芸術体験」コースやTASで行っている講座と合わせてご活用ください。